オンライン若手キャリア座談会 2024年9月
「認知症研究を知る若手研究者の集まり」を主催されている若手研究者育成委員会の先生方に集まっていただき、座談会を開催いたしました。第1回同様、先生方に、認知症研究に関わるようになったきっかけについてお話しいただきました。それに加え、抗アミロイドβ抗体薬が臨床的に使えるようになった認知症診療の転換期に、多彩な研究を第一線で展開される先生方が、何を考えて研究を進めておられるのか、ざっくばらんにお話をしていただきました。
参加者( )内は大学卒業年度
島田 斉 新潟大学 脳研究所(2003年卒)
堀 由起子 東京大学大学院薬学系研究科(2004年卒)
祖父江 顕 名古屋大学環境医学研究所(2014年卒)
中野 将希 滋賀医科大学 神経難病研究センター(2012年卒)
富田 泰輔 東京大学大学院薬学系研究科(司会、基礎研究促進委員会)
木下 彩栄 京都大学大学院医学系研究科(広報委員会)
自己紹介
富田:
皆さん、今日はお集まりいただきありがとうございます。今回は、「認知症研究を知る若手研究者の集まり」を主催されている若手研究者育成委員会の先生方にお集まりいただいて、これまでのキャリアについて話していただこうと思います。最初に、今やっている研究を簡単に紹介していただければと思います。

島田:
新潟大学の島田です。私が今やっている研究は、認知症、特にアルツハイマー病などの神経変性疾患の原因になっているような患者さんの脳内にたまる異常なタンパクとか、あるいはそれが原因になって起こる炎症とか神経伝達機能異常とか、脳の中の変化をPETという検査を用いて画像で評価する研究を行っています。
富田:
基礎研究からのトランスレーションというか臨床よりというか、そういった研究ですね。
島田:そうですね。技術開発から、それを実際に人の臨床研究まで持っていくというようなトランスレーショナルスタディは、まさに今やっていることです。

中野:
滋賀医科大学神経難病研究センターの中野将希です。私の研究内容は基礎研究となっています。対象としているのはアルツハイマー病ですけれど、皆さんご存知の通り、老化は神経変性疾患全体の最大のリスクと言われております。私は脳老化ではなくて、個体老化の観点から脳内Aβ蓄積を制御する分子を見つけ出して、新たな治療・予防・標的になるかを解析しています。また、新しいバイオマーカーを提示することを目指して行っています。

祖父江:
名古屋大学環境医学研究所・病態神経科学分野の祖父江顕と申します。私はアルツハイマー病と神経炎症の関わりについて研究しております。具体的には、アルツハイマー病の患者さんの病理脳から抽出したRNAとアルツハイマー病のモデルマウスのミクログリアから抽出したRNAを用いて次世代シークエンスを行い、共通して変動する遺伝子を同定し、その関連試薬をアルツハイマー病のモデルマウスに投与して認知機能や病理変化を解析しております。

堀:
東大薬の堀です。私も完全に基礎研究で、認知症の発症メカニズム解明と、それに基づいた治療法の開発といった基礎研究をやっています。対象とする疾患は、アルツハイマー病やタウオパチー、シヌクレイノパチーなどの認知症に限らず、幅広いです。私の興味がアミロイドということもあって、末梢臓器にアミロイドが蓄積する疾患も対象としています。培養細胞やモデルマウスを用いた基礎研究がメインです。
これまでのキャリアについて
富田:
それでは、今の先生たちのご研究に至るまでのこれまでのキャリアについて伺いたいと思います。島田先生は、MD(医師)というバックグラウンドで、その前に基礎研究も手掛けられて、またこうやって臨床の方で実際に、特にDMT(疾患修飾療法)が出てきて重要性を増した画像診断・バイオマーカーというところを手がけるようになったキャリアについて、簡単に紹介していただけますか?
島田:
私は2003年から脳神経内科の臨床医として働き始めましたが、その時から特にレビー小体型認知症とかパーキンソン病関連の認知症の方が非常に多彩な症状を呈しているのが非常に印象的で興味深いなというふうに思って、認知症の分野に関心を持ったことが入り口になりました。私の最初の上司が当時大学院でPETイメージング研究をしていまして、自分の患者さんのPETを撮っていただく機会があった時に初めてこの世界に触れて、イメージングっていうのが非常に面白いし、可能性を秘めた研究ツールだなと思ったのを覚えています。というのも、認知症もそうなんですけど、やっぱり脳の病気っていうのは、わかりにくいとか難しいっていうイメージを持たれがちだと思うんですが、その一つの要因は脳の中で起こってることが見えないからわからないっていう側面があるのかなと。一方で、PETとか画像で見ると脳内環境の異常がつぶさにわかると。それを見れば、確かにこの患者さんは脳の調子が悪くなっているぞというのが説得力を持ってわかって、イメージングでもともと興味を持っていた認知症への理解を深められるんじゃないかなと思い、2005年から大学院に入って今の研究を始めて、今に至るという感じです。
富田:
画像を見て面白いと思うっていうところは一つキーポイントかなと思います。臨床家として認知機能の低下というのを認知症とか神経変性疾患で重視するというのは当然だと思いますけど、そこに加えて画像でわかることは何だと思いますか?
島田:
そうですね。「百聞は一見にしかず」という言葉がありますけど、やっぱり目で見て変化をしているというのは、これに勝る説得力ってないと思います。我々はもちろん知識としてはアルツハイマー病の患者さんの脳の中でこういうことが起こっているよというのを頭では理解をしているわけですけども、それが実際に自分の目の前に座っていらっしゃる患者さんの脳の中で確かにそういうことが起きているんだというのは、医師であっても実感しにくいところがあります。自分が診察をした患者さんの脳の画像を見て、自分が診た患者さんの症候と病理が一対一に対応しているっていうのを見た時に、頭ではわかっていた認知症の病態というものが、臨床の患者さんとダイレクトに結びつくという、そういう理解の助けになった印象があるので、そういう意味で病態の理解を深めるのに、画像というのはいいモダリティーなんじゃないかと思います。
中野:
アルツハイマー病に対しての研究の転機は、学部生時代に井原康夫先生(*1)の研究室に卒業研究で入ったことと思います。大学の学部が新しくできた一期生ということもあって、かなり丁寧に教えてもらったことと、今思えばなんですけど、かなり偉大な先生だということです。その時はAβ産生に対する基質特異性の観点からを研究してたんですけど、今後どうしようかなというところで、指導教官の舟本聡先生(*2)に相談したところ、「君は外に出て荒波にもまれた方がいい」という助言もありまして、外部に進学しようと思いました。せっかく修士課程博士課程に進むので、アルツハイマー病だけじゃなくていろんな疾患を対象にしているところで、いろんな知識・見解を身につけようかなということで、京都大学生命科学研究科の垣塚彰先生(*3)の研究室に進みました。そこでは、パーキンソン病に焦点を当てて代謝、特にATPとの関係を研究していました。修士課程から、別になにか教えてくれるわけでもなく、結構厳しいところだったんですけど、今思ったらかなりいい経験になっていたのかなと思っています。その中で、代謝低下と神経変性疾患というキーワードが自分の中では気になっていて、代謝低下と神経変性疾患両方ともに共通して老化っていうのが関連しているだろうということもあって、学位取った後、老化に焦点を当てた研究をしたいなと思い、いろいろ探していました。その時に偶然に、今の滋賀医科大学の西村正樹先生(*4)の研究室で募集があって書類等を出したら、すぐに返事が返ってきて面談をしたりして、ぜひ来てくださいということで今に至っているという形になります。
富田:
中野先生は一つの研究室でずっとやるというより、研究室変わっていろんなものを見てこられたわけですね。欧米だとそういうキャリアの進め方っていうのは比較的当たり前ではあると思います。いろいろ研究室を見てきたということに関していい面、悪い面があったと思いますけど、簡単にコメントもらえますか?
中野:
そうですね。悪い面としては、やっぱり新しい環境になって一からということになるので、どうしても移ってから一年、二年っていうのは起動にのせる期間としてトータルの研究生活で見ると、多少ロスになるのかなとは思います。ただ、良い面としては、同じ研究室だと大概のメンバーは同じ方向を向いて研究をしているんですけど、違う研究室に行くと、また全然違う方向からの見解と意見なり考えがあるので、客観性が持てるのかなと個人的には思ってます。
祖父江:
私はもともと認知症研究を志してはおりませんでした。大学時代は大阪薬科大学(現在の大阪医科薬科大学)に在籍しており、授業で中枢神経疾患の治療薬の殆どが対症療法の域にとどまっていることを知り、漠然とですが、神経の研究に興味を持ちました。大学5年生の研究室配属の時に中枢神経薬理を研究している薬品作用解析学研究室(主宰:大野行弘教授)(*5)に入り、セロトニン関連試薬をパーキンソン病モデルマウスに投与して行動解析をしておりました。行動解析は目に見えて変化がわかるということで、非常に興味を持ち、大学卒業後に行動解析の知識をより深めたいということで、2014年に名古屋大学医療薬学研究室(主宰:山田清文教授)(*6)に入りました。そこでは行動解析を通して統合失調症など精神疾患とグリア細胞の関連について解明していくということをやっておりました。学位取得後は大学院で学んだグリア細胞についてより知識を深めたいということで、2018年から現在まで名古屋大学環境医学研究所・病態神経科学分野(主宰:山中宏二教授)(*7)で今のテーマであるアルツハイマー病とグリア細胞の関わりを研究しております。このように、認知症の研究を志すというよりは、行動解析のような解析手法であったり、あるいは治療標的となるようなグリア細胞に興味を持ち、認知症研究に行き着いたというような感じです。
富田:
PhDベースだと比較的あることだと思いますけど、それぞれ違う分野で研究してきたことを今の研究に役立てるという経験をされてきたわけですね。それぞれ違うところで違う考え方を学んできて、今認知症研究をやっているうえで大きな影響をもたらしたものっていうのは何でしょうか?
祖父江:
これまで神経発達障害など神経精神疾患の研究をしておりましたので、認知症研究においてはモデルマウスが症状を呈するまでに時間がかかるということが、これまでの研究との違いで、効率良く実験をしなければならないという点が非常に苦労しているところです。あとは、神経炎症は神経精神疾患も神経変性疾患も疾患横断的に共通するため、今後も神経炎症やグリア細胞に着目し、これまでの経験を活かして研究を進められたらと思っております。
堀:
私はもともと何か病気に関することがやりたいと思っていて、薬学部に行こうと決めました。実際に薬学部に入って学部4年生の時に研究室を決めるんですけれども、その時に明確に病気をテーマにしていた研究室が岩坪威先生(*8)の研究室だったので、迷わず志望しました。なので、実は最初は認知症研究に強い思い入れがあったわけではないんですけれども、入ってからの研究が面白くて。私がもともと実験が好きだっていうのもあったと思いますが、岩坪先生が進めている分子生物学研究が自分の興味にフィットしたことや、直接のメンターであった橋本唯史先生(*9)がいろいろやってみようよっていう先生だったので、楽しくやらせていただいたということもありまして。そのまま認知症の研究をずっと続けているという感じです。博士を取った後は、長寿医療研究センターにいらっしゃった道川誠先生(*10)のラボでポスドクをさせていただきました。どんな基礎研究でも、それが治療につながる可能性があると思えるのは面白いと思っていて、これからもやっぱり治療というのを頭の片隅において研究をしていきたいなと思っています。
今後の研究の見通しについて
富田:
今回は島田先生がMDで、あと三人はPhDベースということで、DMTが出てきて一気にいろんなものが変わってきたと思うんですけど、認知症研究におけるそれぞれの立場から、今後の研究について教えてください。Aβ抗体医薬が出てきて、今後どういうふうに利用するかという臨床現場の問題もあるでしょうし、基礎研究としては例えばドラッグデリバリーなど、今後どういう方向に研究展開すればいいかという問題もあります。それぞれ皆さんが自分の研究バックグラウンドを生かして何をやっていきたいかというのを簡単に教えてください。
島田:
今、Aβの抗体医薬で実際にアミロイドを取って病態に介入することが、ある程度の意義があるだろうということがようやくヒトでPOC(Proof of Concept)が獲得できたと思います。今まで、我々認知症研究者はずっと、動物モデルなどを使って、こういったアプローチがいいんじゃないかと仮説を立ててそれを検証してヒトにもっていこうってやっていたと思いますけれども、それが本当にヒトでできるようになった。これはすごく大きいことだと思います。Aβを取った後の脳病態がどう変わるんだろうか?っていうのも、ヒトで実際に検証することができるので、基礎の先生方が長年温めている、こういうふうにしたらどうなるんだろうっていうアイディアみたいなものをヒトにトランスレーショナルして、そこで出てきた情報をまた基礎に戻す、そういう基礎と臨床との循環というのが今まで以上にすごくスムーズに進めやすいんじゃないかなと。そういった形で研究が進むのを期待しています。僕としては、今は、基礎の先生たちがやられている研究成果っていうのに学んで、こういったのを次ヒトで見れたら面白いなっていうのに対して新しいリガンド開発とかそういうのも独自にやってはいるんですけども。逆に基礎の先生の方から、ヒトでこういうのを見てよとか、こういうのは見れないの?とか、こういうのがいいんじゃないの?っていうようなことをどんどんインプットしていただいて。逆に我々の方も、ヒトだとこういうようなのが出てきたんだけど、これどうなんですか?っていうのを先生方にお返ししてっていうような形で、もっと密に、それこそコミュニケーションを取っていけると認知症研究全体っていうのがさらに盛り上がるかなと期待してます。
富田:
MDの方でそういう視点を持っていただけると、PhDの人は非常にいろいろいろんな意味でやりやすいと思います。中野先生は、今のこの現状を鑑みて何か思うところがあれば。
中野:
一時期Aβを対象としたアルツハイマー病の治療薬としてなかなか成果が出るものがなかったということで本当にAβが重要なのかという問題もありましたけど、抗体医薬のおかげで、少なくともAβを除去すると認知機能低下が予防できるというのは、かなり大きいかなとは思っています。ただ、個人的な疑問としては、やっぱりAβを除去できても認知機能としては30%ぐらいの抑制っていうのが今のところの臨床データなので、100%は難しいのかもしれないですけど、どこまで効果が出せるのかな?というのは、やっぱり基礎研究している皆が気になるところではあります。ただ、私としては、Aβが標的になるうるので、Aβよりも先制的な形で何か介入することができないかというが大事かなとは思っています。私は今そこに焦点を当ててやってるところで、世界中でいろんな方がやられている通りなかなか難しいところではありますが、それが楽しみでもあります。
富田:
今のポイントはすごく大事なポイントだと私も思いますし、特に臨床現場では関わってくるところだと思います。例えば島田先生、今の中野先生のコメントに対して、どうでしょうか?
島田:
中野先生がおっしゃる通り大きい一歩ではあるんですけども、それだけでは一筋縄でいかないなっていう、我々にとっては不都合な真実というのも、証明されてしまったと。ただ、従来はAβだけ取ってもしょうがないとか、いや取ることに意義があるっていうような水かけ論に終わってしまって、実際どうなの?っていうのがわからなかったのが、Aβを取るとそれだけで解決はしないけど全く意味がないわけじゃないよねって、そういう事実が明らかになったっていうのは大きい進歩だと思います。なんでAβだけじゃダメなの?っていうところっていうのも、以前は単純に、タウの神経毒性とかっていうことだけで語られてたものが、Aβとタウのクロスインタラクションとかいろいろな観点から、あるいはAβもどういう毒性かという、さらにその突っ込んだ議論ができるようになったんで、何か我々が目指してきたものっていうのが失敗とかそういうものではなくて、うまくいかなかった知見とかも含めて、我々は大きく前に進めたなと考えています。
富田:
ここにいる人はみんな、認知症研究の歴史を自分たちで見てきていると思うのですけど、その中でこの大きな進歩というか、失敗も含めながら経験として活かしているのは、特に皆さんぐらいの世代にとってはすごく大事なことかなと思います。じゃあ祖父江先生いかがでしょうか。今のこのDMT時代の中で、ご自分の研究とどうつなぐかっていうところをお願いします。
祖父江:
私は病院実習の際に当時の新薬であったメマンチンを調剤したことを覚えております。それ以降、認知症の新規治療薬が出ておりませんでしたが、抗体医薬の登場は認知症治療に光を灯すような存在かと思います。しかし、まだ副作用や薬価、アミロイドPETの必要性など条件や課題もいくつかある印象があります。そのような課題をクリアしていく一方で、グリア細胞などの周辺環境に視野を広げることも認知症の治療薬開発をする上で、重要な手段の1つかと思います。
富田:
新しい対象としてっていうところはチャレンジングで、これは祖父江先生のみならず、世界中で我々も含めてやっているところだと思います。今回のレカネマブ、ドナネマブにいたる、もともとの大きな発見は1999年のDale SchenkによるNature論文というのがあります。いわゆる、active immunizationの論文ですね。で、そこから24年近くかかったっていうのは、やっぱりファーストインクラスっていうところで難しさはあったと思いますが、認知症研究全体に対して良くなかったと思っています。ただようやくAβ、そして次がタウ、それからおそらくシヌクレインとかTDP-43という“たまりもの”を狙っていいだろうというコンセプトとして確立したこともAβに対する抗体医薬は重要でした。じゃあ次に新しい創薬ターゲット、ここで免疫系、炎症系っていう新しい標的を、どう創薬研究に入れていくかということと、それからいかにそれを早く患者様に情報や薬を届ける工夫っていうのは何かありますか?つまり、我々がこの古典的な研究をずっとやり続けていいのかどうかっていうところは、これ、私自身も迷うところで。なんかもっと早く創薬研究というか、薬として開発することはできるんじゃないかっていうのは常に思うんですけど。祖父江先生、なにかいいアイデアがありますか?
祖父江:
なかなか難しいところではありますが、ヒト病理脳とアルツハイマー病モデルマウスにおいて共通して変動する遺伝子に着目すると種のギャップを超えるようなターゲットを見つける近道になるのではないかなと思って、今の研究をしております。
富田:
特にヒトの剖検試料を使った研究っていうのは、おそらく昔よりも今はかなり重要度が増しています。これまでのPhDベースの研究の中では、マウスや、それこそ線虫といったモデルができれば十分創薬に使えるだろうと思ってきたところが、実はヒトで起こっていることはもっと複雑怪奇だったということがわかってきました。そこを一方向だけのドライビングフォース、我々の場合は多くの場合は遺伝子改変ですけど、それだけで全部説明できるわけじゃないっていうことは、やっぱり重要な問題かなと私も思います。そういった意味で、患者様にご協力いただくというか、研究に対して積極的にご協力いただく上でも、我々自身がその研究成果をどんどん発信していくことは必要だなと思います。なので、そういった面で祖父江先生のご意見を素晴らしいと思いました。
堀:
皆さんおっしゃっていたことが私も思っていることなので、なにか新しいことをいうのは難しいんですが。加えるとするなら、私はアミロイドを除去する新しい技術の開発に携わらせていただいているので、抗体医薬に代わる新しい方法として、今開発している技術をうまく実用化にのせられたらと思っています。抗体医薬はまだ様々な問題があることがわかっているので、同じアミロイド除去を目的とするものであっても、より良い方法を追求することにも意義があると思います。また抗体医薬とうまく併用したりして抗体医薬の問題点を補えたりすれば、より良いアミロイド除去治療にできるのではないかなとも思います。同時に、アミロイド除去以外の方向性で新しい治療のコンセプトを提供できるような研究展開もできたらいいかなと考えています。
富田:
そうすると、今の祖父江先生に対する質問と同じですけど、どういうふうにすれば、新しく、かつ早く持っていけるかという問題点がやっぱ出てくるんですけど、そこはどうお考えですか?
堀:
新しくというところは、これまでとは違う視点で新しい分子を早く見つけるということかなと私は思っています。シングルセルなどの研究技術が今すごく発展してきているので、従来よりもいろんな分子が新しい候補として挙がりやすい。世界的にそういう研究基盤ができているんじゃないかと思うので、マウスやヒト剖検脳のそういうデータをうまく利用して、そこから今まで注目しなかったような新しいターゲット分子を見つけられればいいなと考えています。
富田:
なるほど。ターゲットが新しいと、またいろんな副作用とか全部新しいので、結局創薬プロセスとしてはそんなに早くないんだけど。
堀:
それはそうですね。出てきた分子を早く創薬に繋げるという方法は今は答えがないですけど、これまでより治療ターゲットとすることができる候補分子の可能性は広がっていて、そういう新しい分子の探索は従来より広く早くできるのかなと思います。
富田:
新しいものっていう意味ではそうですね。祖父江先生と似てると思いますけど、新しい分子や細胞を見つけていくっていうのはだいぶ昔よりは違うなと思いますね。
今後やりたいこと
冨田:
認知症研究以外も含めて今後やりたいこととか目指してるところを簡単にそれぞれ紹介してもらえばと思いますけど、島田先生からいかがですか?
島田:
これは自分の今始めている研究になるんですけど、今まで僕は、Aβを見てタウを見てシヌクレインを見てと、異常タンパクがたまっているのを見ていたんですけども、今は異常タンパクを分解するような、具体的にはオートファジーとかそういったようなものにターゲットを当ててイメージング薬剤の開発をやっています。僕にとっては少し新しいフィールドに踏み込んだ形になるんですけども、個人的に非常に良かったなって思ったのは、今までと違うフィールドにきたら、新しい研究者の先生たちとの交流とか出会いっていうのが最近増えてまして。島田が最近こういうの始めましたよっていうのをいろんなところでお話しさせていただくと、じゃあ一緒に研究しようよって感じで、新しく共同研究に誘ってもらったりして、新しい研究費とかをいただけたりする機会に恵まれたので、これから新しいことをまた勉強してやっていけるっていうので、ちょっとワクワクしています。いつまでたっても非常にワクワクすることが続いてて、学生の延長じゃないですけど、ずっと学ぶことがあって幸せだなという思いです。
富田:
ワクワクはやっぱり重要ですよね。それはどんなフィールドでもそうだと思います。じゃあ中野先生いかがでしょうか。
中野:
今はAβに焦点当てて研究してるんですけど、大学院の時はαシヌクレインをターゲットにして研究していたこともあって、Aβやαシヌクレインなど凝集タンパク質に共通するメカニズムはやはりあるのかなと思ったりしています。検体の情報とか見ると、アルツハイマー型認知症を単独で発症している方はさほど多くなくて、いろんな形の疾患を併発している方が多いなという印象があるので、私としてはそういう併発している病態の中で、Aβはもちろん、他の凝集タンパク質との関連性とかも見ていった方がいいのかなということは、臨床の先生と関わることが少しずつ増えた中で印象としてあるので、これからはそちらにも手を広げられたらいいなと思っているところです。
富田:
おそらくその混合型認知症っていうのは、老年性という中では必ず出てくる問題点ですし、もっと言えば老年期ですから、それこそ糖尿病とかそういった末梢の臓器の疾患もいろいろ併発している中で、認知症の薬があったからといって、それを本当に使っていいかどうかっていうところは、これから臨床の現場の方で大きな問題になってくるところだと思いますね。ちょっと話がずれちゃいますけど、そういった本当の老年期疾患にどういうふうにアプローチすればいいかというところについて、島田先生、臨床の立場から、祖父江先生、基礎の立場から簡単にコメントいただけますか?
島田:
臨床の立場から言うと、混合病理と、老年者に対する治療介入のターゲットをどこに見つけるかって、すごく重要なポイントだと思ってます。でも、私個人としては臨床的にはあんまり難しく考えすぎない方がいいんじゃないかなっていうふうに考えています。老年者で複数の病理変化が起きているっていうのは、実はそんなに特別な話ではなくて。例えば高齢者を見てみれば、血圧も高くて血糖値も高くて膝も悪くて腰も悪いとかそういう人がたくさんいます。その全てを等しく治療しなければいけないのかというと、当然そういうことはなくて、その病態の軽重というのを評価した上で、必要な治療介入を検討します。脳も基本的にはそれと同じだと思います。アミロイドーシスがあり、タウオパチーがあり、シヌクレイノパチーがあったとしても、この病理がインシデンタルなもので、病態に対して本質的な影響が少ないっていうような評価ができれば、我々は様子を見る。要するにあるから治療するというふうにはならないという感じになると思いますし、ようやくそれが現実にできる時代になってきたってことだと思うんです。だいぶ実際に脳で起こってることの軽重が評価できつつあるようになったので、これからは脳の治療も、体の治療と似たような形でウェイト付けして治療していけるといいなと個人的に思っています。
富田:
祖父江先生お願いします。疾患として、どういうアプローチをすればいいかっていう。
祖父江:
先ほど島田先生が仰ったように、老化が進んでいくと複合的な疾患になっていくと思うので、基礎研究からすると、様々な病態モデルで今開発中の薬を使っていくというのも一つかと考えております。また、各臓器への影響を解析することも今後重要になってくるのではないかと考えています。
アルツハイマー病と言っても、やはり、脳だけにとどまらないと思います。疾患の本当のスタートが脳であるとも限らないので、アルツハイマー病を脳だけの疾患と捉えず、全身性の疾患と捉えて研究をする必要があると思います。早期に微細に変化する末梢バイオマーカーなどを経時的に探索する必要があると考えております。
堀:
私はアミロイドが興味の対象なので、今も少し始めているんですけれど、末梢アミロイドーシスも面白いなと思っています。勉強していくと、結構、アルツハイマー病などの認知症と似たような現象が末梢でも起きていて、疾患に繋がっているということがわかってきました。認知症に限らず、こういう末梢の疾患も見据えながら研究していきたいと思っています。
若手研究者育成の観点から
富田:
今日は特に若手研究者育成委員会ということで、せっかくですので皆さんが今開催されている若手の会などを通して認知症若手研究者の育成についての印象とか、これまでの自分のキャリアを鑑みてこういう出会いが良かったとか、育成の観点で、皆さんの感じているところ、問題点でも全然構わないので、そこを教えてもらえますか?じゃあ、島田先生からお願いします。
島田:
この若手研究者の会はもう12回なんですけど、自分の時にはあんまり参加するチャンスがなくて、初めてタッチした時が運営側でした。僕が院生の時とかは同じ業界の若手の人たちとの交流の場というのがなくて、僕は交流の場に飢えてて。ちょうどその時期は、バイオインフォマティクス業界の人たちが若手の会を非常に活発にSNSとかで盛り上がってやってて、それを傍から見ていいなってずっと思っていました。だから今認知症学会がこういう若手の会で交流の場を作っているのは、今の若い人たちがすごい羨ましいですね。自分のキャリアの時に欲しかったなと思うので。ちょっと宣伝じみたメッセージにはなりますけども、せっかくのこういう機会があるっていうのは、若い人たちが思っているよりもすごく貴重で、人との交流っていうのはなかなか得がたい機会なので、ぜひ積極的に参加してもらえたらと。一回参加して知り合いができると、そこから自分の世界が広がると思うんですよね。研究活動だったり、学会で会った時に一緒に飲んだり、そういう同年代の知り合いっていうのはかけがえのない財産になると思うので。ぜひ勉強しに来るというか、遊びに来てくれるといいなと思います。
中野:
この会自体かなりいいなと思っています。僕はこの会の存在を学生の時は知らなかったので参加はしてないんですけど。この会の一番のメリットは、いろんな学会の若手の会がありますけど他の若手の会と一つ違うこととしては、アルツハイマー病研究でかなり著名な先生方も一緒に参加されて、同じテーブルについてディスカッションできたり身近に話すことができるっていうことかなと思います。また、私は基礎ですけど、臨床の先生方ともかなり交流ができる場で、学生の時に体験してほしいなということもあります。最近だと博士課程に進む学生がどんどん減ってきているということもあって、こういう会を通して、少しでも楽しみになりを経験してもらったら、博士課程に進んでみようかなという人も多少なりとも増えるんじゃないかなとは思っているところです。
祖父江:
博士課程っていう話が出てきましたが、薬学部も博士課程に進む学生が少ない状況です。六年間学んだ後に更に四年間研究をするという人がなかなか少ない中、若手の会に参加してみると、結構、薬学部の学部生も参加してくれています。
そういった博士課程に進学する人が少ない中でも、研究に触れるような機会であったり、刺激を受けるような機会ということで、認知症研究を活性化する上ではいいことだと思います。
堀:
若手研究者の会の参加者のメインは大学院生ではあるんですけれども、大学一年生とか二年生とか、まだ研究を始めていないようなすごく若い人たちも参加してくれることがあります。そういう若い人たちにもっと宣伝ができたらいいなと思っています。研究を始める前の人達が、少しでも認知症研究を面白いなと思ってくれる機会になればと思います。また、ようやく疾患修飾薬ができてきたという現状があるので、大学とか研究機関だけでなく、製薬企業、さらには政府側の人たちも参加できるようにできたらいいなと思います。そうすると、研究自体だけでなく、研究がどういうふうに薬の開発につながって、どのように実用化されるのかというところを若い人たちが知る機会になって、今後の創薬を進める一助になるのではと考えています。
富田:
ありがとうございます。ぜひ次回以降の企画にはそういったものも加えていただければと思います。皆さんのいろんなご意見とかコメントをうかがって、いろんな人と出会う中で認知症研究の方に向かってきて、今、さらに若手を育成しようという気持ちが見えてきて、私はとても嬉しく思いました。今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さん、どうもありがとうございました。
Online座談会の様子 (2024年9月)
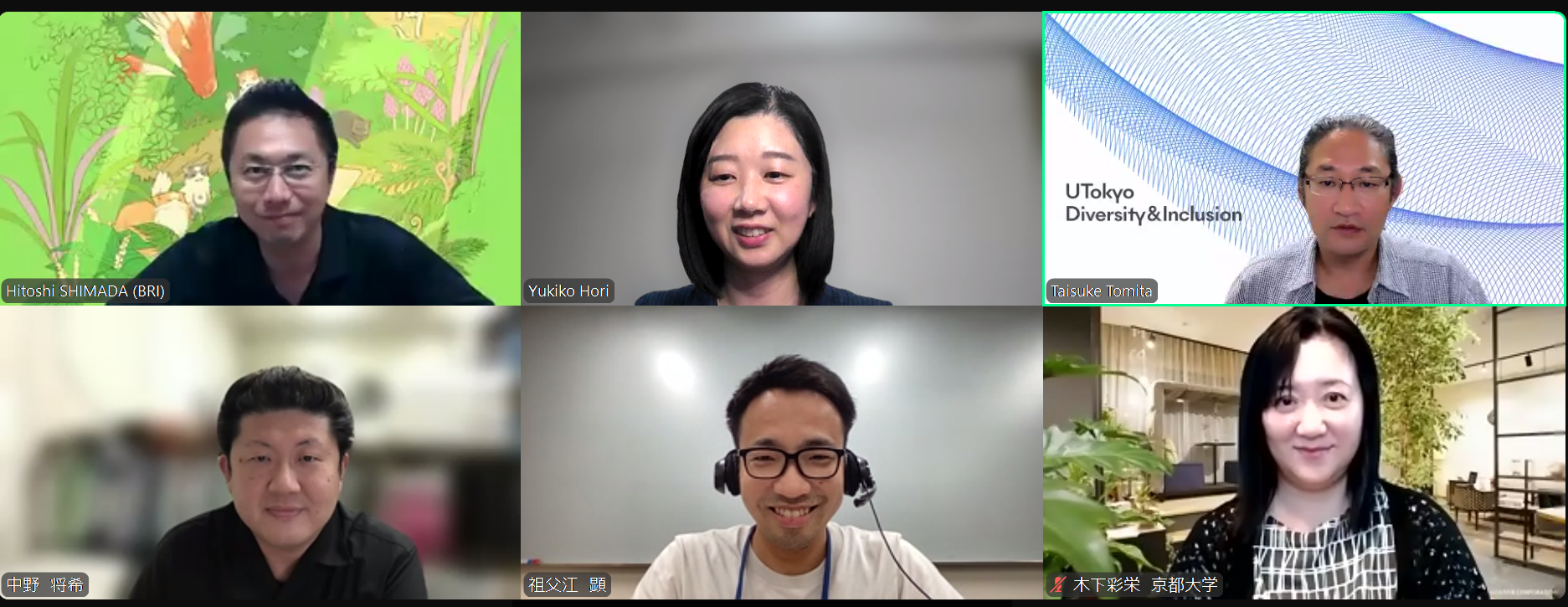
<脚注>
DMT:Disease modifying therapy
1.井原康夫:認知症学会 元理事長、東京大学 名誉教授
2.舟本聡:同志社大学生命医科学部 教授
3.垣塚彰:京都大学大学院生命科学研究科 名誉教授
4.西村正樹:滋賀医科大学神経難病研究センター 名誉教授、公立八鹿病院 院長
5.大野行弘:大阪薬科大学 (現在の大阪医科薬科大学) 教授
6.山田清文:名古屋大学 名誉教授、藤田医科大学 客員教授
7.山中宏二:名古屋大学環境医学研究所 教授
8.岩坪威:認知症学会 理事長、東京大学大学院医学系研究科 教授、国立精神・神経医療研究センター神経研究所 所長
9.橋本唯史:国立精神・神経医療研究センター神経研究所 部長
10.道川誠:名古屋市立大学 名誉教授、日本歯科大学 教授



